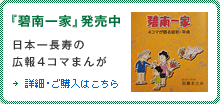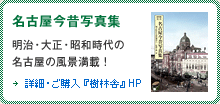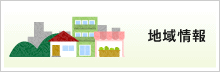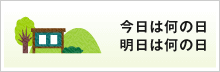2025.10.23
東海の肖像「安場保和~ものづくり愛知 生みの親~」が放送されます
ケーブルテレビKATCHで好評放送中の『東海の肖像』。
東海地方にゆかりある人物や産業、芸術や文化などの歴史、そしてそれを後世に受け継ぐ取り組みなども紹介しながら、この地方の魅力を発信する本格ドキュメンタリーです。
今回取り上げたのは、現在の県知事にあたる第3代愛知県令を務めた安場保和です。

安場保和肖像(写真提供:奥州市立後藤新平記念館)
尾張徳川家が治めた名古屋に県庁を置く愛知県は、明治新政府にとって統治が難しい“難治県”と呼ばれます。
地租改正を推し進める政府に対し、愛知県でも住民からの反発が起こります。
それを解決する手腕を買われ、安場が第3代愛知県令に任命されます。

現在の愛知県庁
1875年(明治8)に愛知県令に赴任した安場が着目したのが、当時の内務卿大久保利通が推進した勧業施策でした。
翌1876年には全国に先駆け、愛知県に勧業課を設置し、殖産興業に努めます。
瀬戸焼は1867年(慶応3)に開かれたパリ万博や、1873年(明治6)に開催されたウィーン万博に出品され、海外から注目を集めていました。
そこで安場は瀬戸焼に目を付け、輸出を後押しするため、ある取り組みを行いました。
詳しくはのちほど…。

三河木綿
さらに安場が注目したのが、三河木綿など県下で盛んに行われていた繊維産業の立て直しでした。
当時、輸入品に押され、衰退していた綿業。
そこで最新式の繊維機械を輸入し、それを運用することで技術者の育成と繊維業の近代化を図る、官営愛知紡績所の誘致にも力を注ぎます。

明治用水頭首工(写真提供:げんぞうアーカイブス)
話は少し遡ります。
江戸後期の1822年(文政5)に都築弥厚によって測量が開始されたものの、弥厚の死によって頓挫した用水建設計画。
その後、伊與田与八郎や岡本兵松によってその計画は継承されますが、明治初めの地方行政体制は不安定で、なかなか受理されません。
しかし、その計画にいち早く可能性を見出し、開発許可を与え、自らも地元の説得や資金集めに奔走したのが安場でした。

名古屋城の金鯱
今では名古屋のシンボルとなっている名古屋城の“金鯱”。
殖産興業や基盤整備を進める安場にとって、地元住民にとっての誇りを守ることも大切な使命のひとつでした。
安場着任当時、名古屋城の金鯱は城から降ろされ、内外の博覧会で人目を惹き付ける役割を担わされていたのです。

博覧会で展示された金鯱(写真提供:げんぞうアーカイブス)
当時、各地で開かれた博覧会に展示された金鯱は、その巨大さと造形美によって、人びとの注目の的となります。
ですが、雌雄別々に見世物として各地を転々とする様が、名古屋の人びとの心を傷つけます。
そんな折、殖産興業を目的に、安場が国内外の優れた産品を集めて展示する、愛知県博物館の創設を計画します。
そしてその開館を記念し、1878年(明治11)に安場が開催したのが愛知県博覧会でした。
瀬戸焼や七宝焼といった県下の特産品はもちろん、産業機械や農産物のほか、手工芸品や美術品、動物園や水族館もありました。
なかでも注目を集めたのが、雌雄一対で展示された金鯱でした。
これを機に名古屋の商人たちが金鯱の返還をさらに訴え、安場が上申した結果、名古屋城に金鯱が戻ることになったのです。

愛知県商品陳列館(写真提供:げんぞうアーカイブス)
こうしてものづくり愛知の基礎を築き、そのアイデンティティも守った安場保和。
ものづくりに欠かせない先端技術や優れた産品を展示する愛知県博物館は、安場の退任後も存続し、1911年(明治44)にリニューアルされたのが、愛知県商品陳列館です。
産業振興という安場が目指した精神が受け継がれたのです。
東海の肖像「安場保和~ものづくり愛知 生みの親~」(30分番組)
放送日時は次の通りです。
地上デジタル121ch
10月24日(金)20:30
10月26日(日)23:00
10月31日(金)20:30
11月も放送があります。
※災害時や特別番組により、放送日時は変更されることがあります。
CS地域情報チャンネルsatonokaでも全国放送!
11月26日(水)19:00 ほか
詳しくはKATCHホームページをご覧ください。